素読のすすめ 第41~45回
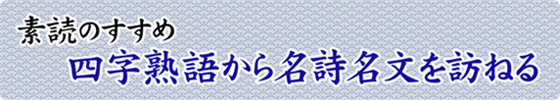
暖かい着物を着、腹いっぱい食べる。生活に不自由のないさま。満ち足りた生活、さらにはぜいたくな暮らし、という意味にもなる。
「暖衣飽食」の反対が「悪衣悪食」(粗末な着物を着、粗末な食物を食べる)だ。
孔子は「士、道に志して悪衣悪食を恥ずる者は
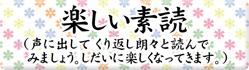
「孟子」滕文公章句上
大意
孟先生(約2000年前の学者)の言はれることに
人には人の道があるということは、暖かい着物を着て、腹いっぱいものを食べて、ヌクヌクとなまけ暮しをして人の道という教えがなければ、とり、けもの、犬、猫と同じである。そこで昔、徳の高い帝王がこれを憂いまして、
1、父子の親(親は子のために、子は親のためにかくすという情)
2、君臣の義(使う人、使われる人の間にある道義)
3、夫婦の別(夫は家族のために戦い、妻は家族を養い育てる)
4、長幼の序(長上を敬い弱者をいたわるという順序)
5、朋友の信(友だちとの約束は守り、違えることがない)
いわゆる五倫の教えというものを作りました。
鑑賞
現代社会を振りかえってみましょう。
朝、テレビをつければ、着るもの、食べるもの、住むところ、その生活、見る側の収入に関わりなく、これでもか、これでもかと、欲求を刺激する画像が際限なく送り出されてきます。
一方、教育の場はどうかと言えば、知識を供給する場はあっても人の道を学ぶことを教育課程に持つ場は見当たりません。頭さえよければ、いい学校に入りさえすれば、いい所に就職出来さえすれば、自分さえ良ければ良しとする風潮を、このまま見過してよいものでしょうか。この現代社会の現状をあなたはどうお考えになりますか。
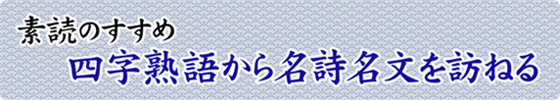
人生は
禍が来たかと思えば福が来る。「禍福はあざねえる縄のごとし」と同じ。
次の話に基づく。
国境近くに術使いがいた。飼っていた馬が逃げたので、人が慰めると、いや禍とは限らないと答える。果してその馬が
良い馬が来たので、その息子が喜んで乗るうち、落馬して足を折った。人がおくやみに来ると、いや禍とは限らないと答える。
やがて
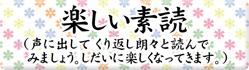
「
語釈
○塞翁…とりでの近くに住む老人。「塞」は国境の砦「翁」は老人。
○塞上…とりでのあたり「上」はほとり、(その付近)の意
○善術者…占いなどの上手な人。予言をする人の意。
○胡…西地方の遊牧民の地。良馬の産地として知られる。
○賀…祝福する
○弔…見舞う、お悔やみを言う。気の毒に思って慰める
○父…ここでは「ほ」と読んで老人の意
○何遽不為福乎…どうして福とならないことがあろうか。
「何遽」は二字で「なんぞ」と読む。
○居数月…数ヶ月たって
○駿馬…足の速い馬、良馬
○髀…太ももの骨、大腿骨
○丁壮…働き盛りの男たち
○弦を控く…弓を引き絞ること
○跛…片足の不自由なこと
○化…ものごとの変化の微妙さ
○深…ものごとの道理の奥深さ
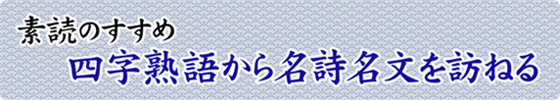
―目的達成のため苦労に耐える―
「
春秋時代、
負けて
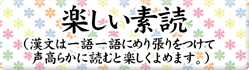
十八史略「臥薪嘗胆」
大意
呉がふたたび越を攻めたとき、闔廬は傷を負い、それがもとで死んだ。
闔廬が死ぬと、その子夫差が王位を継いだ。伍子胥はひきつづき夫差に仕えることになった。夫差は父の仇を討とうと心に誓い、朝晩たきぎのなかに寝起きしてはわが身を苦しめ、出入りのさいには、臣下に
「夫差よ、父が越王に殺されたことを忘れたのか」
といわしめては、復讐の念を新たにした。
周の敬王の26年、夫差は夫椒の戦いでついに越を破った。越王勾践は残兵を率いて会稽山に逃げこみ、夫差にこう申出た。
「どうかわたしを大王の臣にし、妻を大王の妾にしていただきたい」
伍子胥はこの和議を受諾しないよう主張したが、越から賄賂を贈られた呉の大宰の伯嚭は、勾践をたすけるよう夫差に説いた。夫差は伯嚭の言を入れて、勾践を許してしまった。
こんどは勾践が復讐を誓う番となった。帰国するや、勾践は自分の部屋に干した獣のキモを吊りさげておき、いつもそれを口にして苦さを味わっては、
「会稽の恥を忘れはすまいな」と自分自身にいいきかせた。そして国政はすべて大夫の文種にまかせ、自分は賢臣范蠡とともに軍を鍛え、呉への復讐だけに専念した。
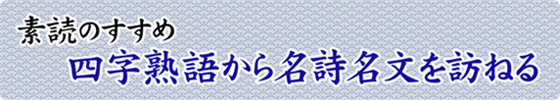
七歩あるく間に詩を作る。作詩が早いこと、詩の才能が豊かなことをいう。
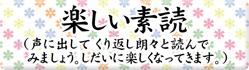
七歩あるく間に作った詩
豆を煮て吸い物を作り、みその漉して汁を作ろうとする。豆がらは釜の下で燃え、豆は釜の中で泣いている。「もともと、同じ根から生れた(兄弟)なのに、どうしてこんなにひどく激しく(私を)煮たてるのですか」
大意
「七歩の詩」とは、「七歩あるく間に詩を作れ、出来なければ殺す。」という兄の文帝(
「豆」が曹植、「萁」が曹丕、「同根」というのは両人がその父(曹操)を同じくしていたことを指す。
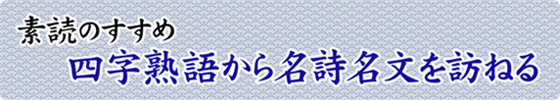
国中に二人といない優れた人。天下第一の人
「国士」は国の中でもっとも優れた人の意。「無双(
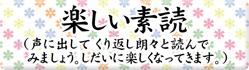
すなわち
「十八史略」楚漢の争い
大意
楚の項梁の軍が淮水を渡って進撃した時、韓信はこれに身じた。かれは何度となく項羽に献策したがいっこうに採用されない。ついに意を決して、楚を去って漢に投じ、ようやく治粟都尉に任命された。大臣の蕭何とは何度となく語り合い、蕭何は、韓信の人物を深く認めるようになった。
やがて、漢王は、漢中に封ぜられて南鄭に向けて出発したが、将兵の多くは望郷の思いにかられ、口ぐちに故郷の歌を歌った。
やがて逃亡する者が続出した。韓信も動揺した。
考えてみれば、蕭何は何度も自分を推挙してくれたが、漢王は一向に自分の策を聞き入れてくれない。ここらが潮時とみて韓信も逃げた。
蕭何は韓信が逃げたと知るや自分でこれを追いかけた。と、ある者が漢王に報告した。
「蕭丞相が逃げました。」
漢王は怒った。丞相に逃げられたのでは左右の手をもぎ取られたようなものだ。だが、ほどなく蕭何はもどって、漢王に拝謁した。漢王はどなりつけた。
「お前まで、なぜ逃げたのか。」
「韓信を追いかけたのです。」
「いままで逃げた将軍は何十人もいる。なのに、お前はだれも追わなかったではないか。韓信を追いかけたなどと、でたらめをいうな。」
「あんな将軍どもなら、いくらでも代わりがいます。だが韓信はふたりといない国士です。わが君がこれから先、いつまでも漢中の王で満足されるなら、韓信は必要な人物ではありません。だが、天下を取ろうという決意でおられるなら、かれをおいて他に相談相手はありません。」
「やがては東方へ撃って出るつもりだ。いつまでもこんなところに居られるものか。」
「そのご決心ならば、韓信にそれなりの任務をあたえることです。そうすれば、かれもとどまりましょう。さもなければ、いずれは韓信は去ってしまいますぞ」
「それならば、お前の顔を立てて、将軍に取り立てよう。」
「いや、将軍ぐらいでは……」
「では大将軍に取り立てよう。」
「そうして頂ければ幸いです。ついては、このさい、ひとこといわせていただきたい。わが君のわるい癖は、傲慢で礼を欠いておられることです。大将軍を任命されるのでも、まるで子どもを呼びつけるくらいにしかお考えにならない。韓信が逃げたのもそのためです」
漢王はこの意見を聞き入れ、礼にはずれぬよう、大将軍任命のため祭壇式場を設けた。
これを見て、将軍たちはみな喜んだ。だれもが自分が大将軍に任命されると思ったのである。だが、いざふたをあけると、これが韓信だったので、全軍はあっけにとられた。
